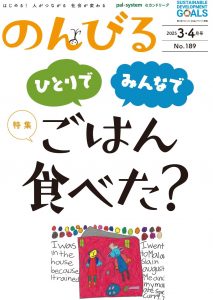やまうち・わかな 1977年神奈川県生まれ。武蔵野美術大学短期大学部美術科卒業、同専攻科美術専攻修了。
福島、広島などでフィールドワークを重ね、国内外で個展を開催。子どもたちに向けた「いのちの芸術鑑賞授業」や
移動型展示講演会なども企画している。2021年には「牧場 放(はなつ)」で東山魁夷日経日本画大賞入選。
著書に『いのちの絵から学ぶ 戦争・原発から平和へ』(彩流社)。
福島、広島、長崎、ビキニ環礁、沖縄などをテーマに、創作活動に取り組む山内若菜さん。
作品には生きとし生けるもの、すべてのいのちの営みと希望があり、
平和への祈り、画家としての覚悟が息づいています。
聞き手・構成/濵田研吾 写真/堂本ひまり 撮影協力/都立第五福竜丸展示館
希望と未来を絵のなかに
─「山内若菜展 ふたつの太陽 命を紡ぐちいさな生きものたち」(都立第五福竜丸展示館)を拝見しました。ビキニ水爆被災(※1)70年の節目に描いた「ふたつの太陽」(上写真)は、15メートルを超える大作です。
「ふたつの太陽」は折りたたんで、大きなバッグにつめて、3回にわけて電車でここまで持って来ました。絵が旅をして、いろんな場所に展示して、観てくれた方が共鳴してくれる。「旅する絵」が、私の画家としての生き方と似ているような気がします。私は派遣業も入れると20年ぐらい、ブラック企業で不安定な働き方を続けていました。どこにいても、どんな状況でも、何かしら描いていました。「持たざるものの表現」というか、悩みながら描き、発表し、「世の中を変えるんだ」と叫んでいた気がします。刹那的で、表現に突っ走るタイプなんです。
─著書を拝読しました。原発事故後の福島での体験が、画家として「いのち」と向き合う原点になったそうですね。
ブラック企業で働いていたときは、人ではなく、物扱いされていました。そんなとき、東日本大震災が起きたんです。被ばくし、殺処分される福島の牛たちを見て、「あれは自分だ」と痛感しました。最初は想像だけで、福島のことを描いていました。 2013年に初めて、原発事故で全村避難を強いられた飯舘村の牧場を訪れました。目の前で馬が何頭も死に、流産や死産も多い。明らかに被ばくの症状なんです。取り憑かれるように福島に通い、色のない黒い絵ばかり描きました。今から考えると、それが画家としての出発点でした。
─絶望、怒り、悲しみを描きながらも、山内さんの作品には自然、動物、人間の美しさが込められています。
「ふたつの太陽」には、被ばくして怒りを叫ぶ樹木を描いています。私は、その樹木が美しいことを描きたい。見過ごされてきた小さき声を拾い上げ、生物多様性を含めた世界のいのち、その絡み合いを、自然の光とともに伝えたいんです。 福島に通い始めたころは、絶望と怒りをキャンバスにぶつけていました。それが当時の私には、必要な表現でした。「黒の時代」をへて、今の色づかい、私の表現がある。子どもたちに向けた「いのちの芸術鑑賞教室」も、最初は震災の記憶を伝承する目的で始めました。それが「いのちの授業」へと、少しずつ変化していったんです。
─いのちと光、それは希望と未来でもある。
はい。「希望はここにある」という指針を、絵を通して示したい。私が思い描く理想の世界や思想を発露しないと、一歩進んだ絵になりません。2019年、福島に1ヵ月間滞在して、牧場の仕事を手伝いながら描き続けました。コロナ禍となり、どんな美と世界観を発表していくのか、ゆっくり考えることができました。弾けるように色を使い始めたのは、そのころからです。

山内若菜 絵・文『いのちの絵から学ぶ 戦争・原発から平和へ』
(彩流社、税込2,200円)
・・・続きは『のんびる』3.4月号特集をご購読ください。
【バックナンバーのご注文】 富士山マガジンサービスよりご注文ください。 【定期購読(年6冊)のご注文】 ・パルシステム組合員の方:ログインしてご注文ください(注文番号190608) ・パルシステム組合員でない方:こちらからご注文ください